【コラム】 吉田奈緒子|“ギフト”がつくる循環 アイルランドの「カネなし男」が引き出した、ローカルな経済圏の可能性
イギリスでフリーエコノミー運動を創始したマーク・ボイル氏の著書翻訳をし…

イギリスでフリーエコノミー運動を創始したマーク・ボイル氏の著書翻訳をし…

SNSやメールで、気軽に贈り物ができる「ソーシャルギフト」。横ばいが続くギフト市場で、この領域が急進…

福岡県の久留米で靴を製造し続ける「ムーンスター」。身近なところでは学校の上履き、専門分野では厨房や医…

福岡県の第三都市・久留米に本社を構えながら、明治期から靴づくりを続ける「ムーンスター」。そのブランド…

文房具にとって、機能面はもちろん、バリエーション豊富なデザイン性も大きな魅力のひとつ。ときにプレゼン…

東川町の町長らに伺ったデザインミュージアム構想。その中心を占めているのは、椅子研究家の織田憲嗣さんに…

パン屋さんの焼き立てのパンを食べた経験、皆さんはどれぐらいあるだろうか。思い返してみると、私は…

急須の再発明 — nana’s green teaを運営する七葉は、新しい急須体験を目指す…

サントリー食品インターナショナルは、水道水を瞬時においしい水に変えるミネラルinウォーターキャ…
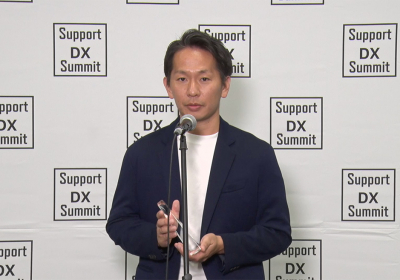
カスタマーサポートのデジタル化を推進する、一般社団法人サポートデジタル協会は、デジタルチャネ…

2020年11月20日にオンラインイベント「新時代のD2Cブランドの作り方」が開催された。同イ…

顧客体験を考える上で、サービスや商品を“提供する人”の存在は無視できない。
たとえば、サービス提供者の熱心な姿は顧客に影響する。逆に、顧客が優れた体験をできている状態をみて、サービス提供者に影響をもたらす。…

XDを運営するプレイドが、J-WAVE(81.3FM)の『TOKYO MORNING RAD…

XDを運営するプレイドが、J-WAVE(81.3FM)の『TOKYO MORNING RAD…

XDを運営するプレイドが、J-WAVE(81.3FM)の『TOKYO MORNING RAD…

2019年は、あらためて「サステナブル(持続可能)」という言葉が注目を集めた年だった。博報堂が2019年11月に発表した「生活者のサステナブル購買行動調査」…

朝起きて、布団に潜り込んだまま「Instagram」のアイコンをタップする。アプリを起動し、ストーリーズを流し見でチェック…

本記事は、中国のテクノロジーを中心とする社会動向に精通した家田昇悟氏の寄稿記事。2010年代初頭から中国におけるIT化…